全国各地で相次ぐクマによる人身被害。
「またクマが人を襲った」と報じられるたび、私たちは“危険な動物”としてクマを恐れます。
しかし、神奈川県山北町の猟師たちは、別の視点からこの問題に立ち向かっています。
「クマは人を襲いたくて襲っているんじゃない。生きるために山を下りてくるだけだ」――。
そんな思いから、彼らはクマを里から山へ帰す“共生の森づくり”に取り組んでいます。
87歳の現役猟師・杉本一(すぎもと はじめ)さんが中心となり、山の再生を目指す活動が静かに広がっているのです。
87歳猟師・杉本一さんの挑戦
神奈川県山北町の猟師・杉本一さん(87)は、長年の経験から、「クマが増えたのではなく、人間が森を変えてしまった」と語ります。
戦後、全国で進められた拡大造林によって、スギやヒノキなどの針葉樹が大量に植えられました。
しかし、輸入木材の増加や国内需要の低下で伐採されずに放置され、山は日差しが届かない人工林に。
若草もドングリも育たず、野生動物の餌が極端に乏しくなったのです。
「スギとヒノキばかりの山じゃ、クマもシカも生きていけない。人間が山を変えたから、クマが里へ降りてくる。俺たち猟師にはその現実が見えている」と杉本さん。
年に3回ほどクマを目撃するという杉本さんは、危機感を募らせながらも、「クマを駆除するのではなく、森を治すことで人とクマの距離を戻したい」と語ります。

クヌギ・クルミの植樹活動
杉本さんは10年前、狩猟仲間たちとともに、広葉樹であるクヌギの実(ドングリ)を集め、苗木を育てて植樹する活動を始めました。
目的はただ1つ――「クマが人里に降りなくても生きていける山を取り戻す」こと。
しかし、近年はドングリそのものが森で見つからなくなり、活動は困難に。
そんなとき、孫で猟師の鈴木康之さん(38)が偶然“幻のクヌギ”を見つけます。
車で走行中、ドングリを踏む音に気づいて確認したところ、一面にドングリが落ちていたのです。
その場所で2つの買い物かごいっぱいのドングリを拾い、約2,000個の実から苗木を育成。
今年3月には、ボランティア約80人が参加し、大野山周辺でクヌギ1,400本・クルミ100本を植樹しました。
活動を引き継いだ豊猟会の豊田里己会長(67)はこう話します。
「スギとヒノキだけの森では、クマもシカも餌を得られない。人間の都合で作った森を、人間の手で元に戻すしかないんです。」
この地道な努力が、山の命を少しずつ取り戻しているのです。
人間とクマが共に生きる森へ
「クマだって、人間を避けて生きたいんだ。」
杉本さんのこの言葉には、全ての思いが込められています。
人間と野生動物の“境界線”が曖昧になった今、必要なのは恐怖ではなく理解。
クマが人里に現れる背景には、餌不足という生態系の異常があるのです。
杉本さんが10年前に植えたクヌギは、すでに実をつけ始めています。
その姿は、「共生の森づくり」が確実に成果を上げている証です。
高齢ながらも活動を続ける杉本さんは、各地のクマ被害地域にも苗を配布し、「駆除よりも森の改善を」と訴え続けています。
ネット上での反応と声
ネット上では、この取り組みが反響を呼んでいます。
・「クマのせいじゃない、人間が森を壊した結果だよね」
・「こういう猟師さんの声をもっと広げてほしい」
・「森を再生することが、最も現実的な“クマ対策”だと思う」
・「子供にも伝えたい話。人と動物の関係を考え直すきっかけになる」
多くの人が、“クマ=悪者”という単純な構図に疑問を投げかけ始めています。
SNSでは「#共生の森」「#クマ被害対策」「#森の再生」といったハッシュタグも広がり、共感の輪が少しずつ大きくなっています。

まとめ
クマを追い払うのではなく、クマが山で生きられる環境を取り戻す——。
その地道な取り組みが、人と自然の新しい関係を築く第1歩です。
人工林の放置、森の飢え、そして人里への出没。
それらは全て「人間の暮らし」と無関係ではありません。
「クマを駆除するより、森を育てよう」
杉本さんたちの活動は、私たちに“共生”という選択肢を改めて問いかけています。


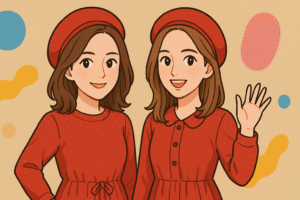







コメント