北海道の積丹町で、ヒグマの駆除をめぐって町議会副議長と地元猟友会が対立し、猟友会が出動を拒否するという異例の事態が発生しました。
この問題は、地方行政の信頼、議会と住民の安全、そして野生動物対策という重要な要素が絡む重大な社会問題となっています。
11月7日、副議長はようやく町議会で謝罪を行いましたが、その真意と今後の対応が注目されています。
副議長の態度の変化と町議会での謝罪内容
2025年9月、積丹町議会の副議長・海田一時氏が、ヒグマ駆除現場での発言をきっかけに猟友会と対立。
発言内容は「こんなに人数が必要なのか」「金もらえるからだろ」「議会で予算も減らすからな」「辞めさせてやる」といった威圧的なもので、これが猟友会の強い反発を招きました。
以降、猟友会は町の出動要請に応じない方針を堅持しています。
当初、海田副議長は「謝罪するつもりはない」「僕は悪くない」と強硬な態度を示していましたが、
11月7日に行われた町議会の産業建設常任委員会にて、「私の不用意な発言から猟友会員や役員のみなさんなどにご迷惑とご心配をおかけした」と公式に謝罪しました。
また、松井秀紀町長も「町政を預かる立場から心からおわび申し上げる」と謝罪を表明。
しかし、猟友会側からは「直接の謝罪がない」「現場介入に対する誓約もなし」との不満が残っており、信頼関係の修復には至っていません。

猟友会の役割とヒグマ被害対策の現実
猟友会は、野生動物の駆除・安全確保・地域防災の最前線で活動する重要な団体です。
特に近年、北海道ではヒグマの出没件数が増加しており、積丹町でも2025年は過去最多の出没報告が出ています。
こうした状況下での猟友会の出動拒否は、住民の命と安全に直結する深刻な問題です。
駆除現場では安全確保のためのルールが定められており、猟友会がその判断で関係者を退避させることは当然の措置。
しかし副議長はそれに対して反発し、立場を利用して圧力をかけた形となり、事態を悪化させました。
再発防止と信頼回復への道
積丹町は、今回のトラブルを受けて「ヒグマ捕獲対応マニュアル」の作成に着手。
出動再開と信頼回復に向けて、今週中の完成を目指しています。
このマニュアルでは、駆除現場への立ち入り制限、安全基準、関係者の役割などを明文化する予定です。
信頼回復には、マニュアル整備だけでなく、猟友会への誠意ある対応が不可欠です。
副議長が猟友会に直接謝罪し、再発防止の意思を明確にすること。
そして町議会全体としても猟友会との協議体制を強化し、再び協力関係を築く努力が求められます。
ネット上での反応と声
この問題はネットでも大きな反響を呼び、
・「町議会での謝罪だけでは不十分」
・「猟友会に直接謝れ」
・「議員としての自覚が足りない」
といった批判が相次いでいます。
特に猟友会の立場に立つ意見が多く、
・「危険な任務を担う人たちを軽視するのは論外」
・「クマは待ってくれない。早く対応体制を整えてほしい」
など、現場のリアリティに対する共感と懸念が目立ちます。
議員の発言1つが地域の安全に直結することへの問題提起でもあり、行政・議会の説明責任や行動改善が強く求められています。

まとめ
「猟友会出動拒否問題で副議長が町議会で謝罪」というニュースは、単なる地域トラブルにとどまらず、地方政治と住民安全、そして野生動物対策における協力の重要性を示しています。
今後、積丹町がどのように信頼を回復し、猟友会との関係を再構築していくかが注目されます。
この1件は、全国の自治体にとっても「行政と専門団体との連携のあり方」を見直すきっかけとなるでしょう。




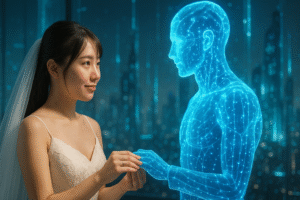





コメント